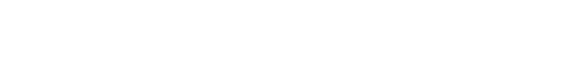| 開催時間 | テーマ | 開催内容 |
|---|
| 10:30?12:30 | なぜ、あの企業は競争に勝ち続けられるのか?
| 世の中にはたくさんの企業が存在しており、日々競争を繰り広げています。
しかし、その中から本当に勝ち上がっていける企業はごくわずかとも言われています。
どのようにしたら勝ち続けられる企業になれるのか、事例をもとに解説します。
適宜グループディスカッションを取り入れ、戦略への理解を深めます。
|
|---|
複利計算と数学
| 複利計算は、銀行にお金を預けるときに、利息を計算するための方法です。
例えば、100万円を銀行に年利率1%で預金すると、1年後には1万円の利息がつき101万円の預金になります。
次の年には、この101万円にまた利息がつくので、どんどんお金が増えていきます。
これが複利計算の仕組みで、この預けたお金が増えていく様子を等比数列を使って表すことができます。
この講義では、複利計算による預金や借金返済方法の仕組みと等比数列との関係を説明します。
|
あなたは地域社会にどうコミットしますか?
― 地域社会における自身の役割を考える ―
| 少子高齢化と人口減少の進展著しい我が国では、地域社会を持続可能なものとしていくために、
世代を問わず誰もが可能な範囲で何らかの役割を担い、皆で互いに支え合っていくことが重要とされています(地域共生社会)。
地域社会において、皆さんのような若い世代はどのような役割なら無理なく担い継続できると思いますか?
また、その為にはどのような事柄が必要になるでしょうか?この企画では、
事例(加藤ゼミが東松島市で行ったフィールドワーク)等を素材に個人ワークやグループワークを行い、
若い世代が主体的に地域社会へ関わることについて考えます。
参加した皆さんにとって地域社会との関わり方を自分事に捉える機会となれば幸いです。
|
| 13:30?15:30 | 午前と同じ | 午前と同じく3講座を行います。 |
|---|
たくさんのご要望をいただき、経営法学科では5月に行った「入試対策講座」を再び実施いたします。
入試のイメージがわかない方や不安な方は、受講をオススメします。
| 10:30~12:30 | 「入試対策講座」
経営法学科が受験生に求める能力や適性、在学生による入試体験談などについて
①総合型選抜で入学した在学生2名の入試体験談
②総合型選抜で入学した在学生1名による入試デモンストレーション
※「入試対策講座」は、7月26日(土)のオープンキャンパスに参加した方のみが申込できます。 |
|---|